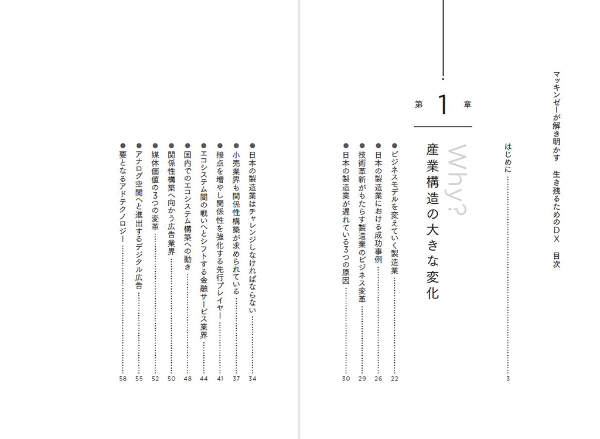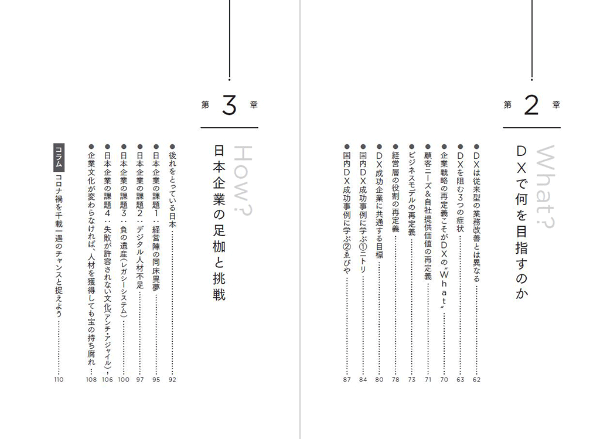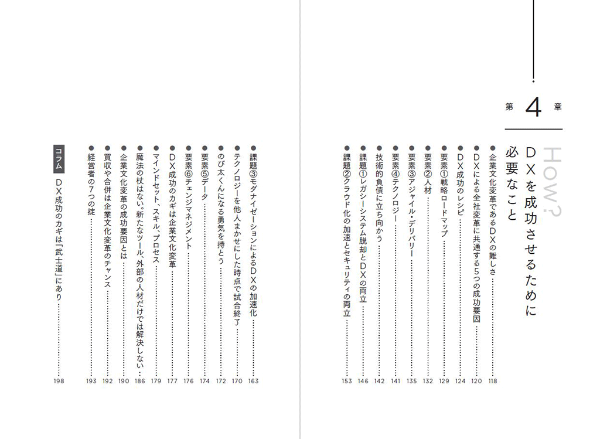その本の「はじめに」には、著者の「伝えたいこと」がギュッと詰め込まれています。この連載では毎日、おすすめ本の「はじめに」と「目次」をご紹介します。今日は黒川通彦さんほか編著の『 マッキンゼーが解き明かす 生き残るためのDX 』です。
【はじめに】
DXの本質は、企業文化変革
私たちは、様々なメディアを通じて、繰り返し「マッキンゼーが考えるDX(デジタル・トランスフォーメーション)の本質は、企業文化変革である」と発信してきました。
企業文化変革とは、一言でいえば、企業が生き残るための破壊と創造です。長年、市場で生き残ってきた企業は、それぞれ独自の歴史と企業文化を持っています。そして、それが会社の常識となり、従業員の行動様式や共通認識として定着し、安定した会社運営を支えています。
社会環境・市場環境が大きく変わらない時代は、それで問題ありませんし、むしろ、それが強みでした。しかし、消費者のニーズや社会環境が大きく変化している現在、そして、技術を武器に新興国や次のGAFAが台頭してくるであろう未来に、変化を好まない日本企業は、生き残ることができるのでしょうか?
経営者の方々にお会いしたとき「御社は、いまのビジネスモデルで、あと何年生き残れますか?」という質問をしています。「3年、5年後は生き残れますか?」と問いかけると、「問題ない。いまも利益はそこそこ出ているし、競合もそこまで変化しないし、新興企業も脅威ではない」という答えが返ってきます。ところが「10年後、20年後はどうでしょう?」と質問すると、多くの方が答えに窮してしまいます。その頃には、現経営陣は会社にはいません。10年後、会社の舵取りは、現在40~50代の方々(本書では、次世代リーダーと呼んでいます)にバトンタッチされています。
10年後、あなたが会社の経営を任され、ある日突然、危機が訪れたら、あなたは会社を、急に変革できるでしょうか。危機は思わぬスピードでやってきます。この10年で成長したGAFA、BATHなどのデジタルネイティブ企業は、一気に顧客を囲い込み、産業構造までも変えてしまいました。伝統的企業で生き残っているのは、それに呼応して、いち早くデジタルなど新しい能力を取り入れて、自社のビジネスモデルを変革し、自社の企業価値を高めた欧米の大企業やオーナー企業です。
つまり、DXをきっかけとし、強い危機感を社内に醸成し、自社を破壊し創造し直した企業だけが生き残っているのです。日本では、各企業の置かれている環境は異なり、まだ当分、脅威が感じられない、という業界もあるかもしれません。しかし、来るべき脅威の波に備えて、古くなってしまった企業の常識をいまから変革していかないと、危機が来てからでは、間に合いません。
DXがこれだけブームになり、新型コロナウイルスで世の中の常識も変わりました。いまだからこそ、自社の古い常識を見直しませんか。
私たちは、DXの本質とは、「生き残るための自社の企業文化の破壊と創造による企業価値の向上」だと考えます。もう少し説明を加えるならば、DXの本質とは「DXをきっかけに、世間の常識からみて、古くなった“自社の常識”を自ら破壊すること」。そして「従業員の意識、共通認識、行動様式を、時代に合わせて創造し直すこと」。その結果、「従業員が、消費者・顧客に選ばれ続けることを目的として、自律的に課題解決を行うこと」「最終的に、脅威が来たときに生き延びられるように、自社の企業価値を圧倒的に高めること」であると考えています。
破壊と創造に挑んだ者だけが生き残る
過去30年を振り返ってみると、世界的に比較した日本企業の企業価値は、相対的に下落し続けています。平成元年(1989年)の世界時価総額ランキングでは、日本の企業がTop20の約7割を占めました。それが、2021年5月時点では、アメリカ企業がTop20の約7割を占め、日本企業はトヨタが38位に入る程度です。アメリカ企業は、GAFAが生まれたことで時価総額を伸ばした企業が多い一方、マイクロソフト、JPモルガン、ジョンソン&ジョンソン、ウォルマート、バンク・オブ・アメリカ、コカ・コーラ、ナイキ、ファイザー等、いわゆる伝統的企業であったにもかかわらず、大きく時価総額を伸ばした企業があります。一方で、衰退した企業もあります。
その差異が生じた要因を分析するために、マッキンゼーでは、リーマンショック後に、全体の平均よりも株価を伸ばした「勝ち組」グループと、逆に平均よりも株価を落とした「負け組」グループが、実際にどのような活動をしていたかの比較をしてみました。すると、「勝ち組」は、消費者・顧客により選ばれるために、デジタル、デザイン、アジャイルなどの新しい組織能力獲得に投資を行うことで、従業員をリスキリング(能力の再開発)し、買収やJV(ジョイントベンチャー)を積極的に行い、エコシステムを形成し、デジタルチャネルを使ってより付加価値の高いビジネスモデルヘ転換するなど、要するにDXをきっかけとした、企業文化の大変革を実施していました。
一方で、「負け組」は、リストラや事業売却など、コスト削減に寄与する改善活動のみに終始し、なんとか会社を存続させていました。日本においては、オーナー企業や、ベンチャー出自の企業など、危機感の醸成と、トップダウンがうまく働く企業においては、同様の変革が実施されました。しかし、大多数の大企業においては、失われた20年と称される通り、成長に向けた大きな投資をするのではなく、コスト最適化や業務改善を粛々と実行し、変革ではなく改善に終始してきたために、企業価値は上がりませんでした。つまり、古い企業文化を破壊し、創造し直すことで、自社の提供価値を上げる努力を惜しまず、そのためにビジネスモデルを変化させるような、大きな変革にチャレンジし、従業員が本気で、一丸となって課題解決を実施することで、企業の価値を高められるのだといえるでしょう。
もう「偽物のDX」をしている余裕はない
残念なことに、日本で企業文化変革に成功し、ビジネスモデルを転換するなどして、企業価値を高めるに至った企業は、数パーセントに過ぎないというのが実情です。その理由は、DXで新しいソリューションを導入することや、レガシーシステムを刷新する、いわゆる旧来の「IT化」が目的化しているためです。
その結果、企業文化変革を起こすために始まったという目的が忘れ去られ、間違ったDX、やったふりDXと呼ばれる、業務改善レベルの小さな効果しか生まれない、矮小化されたIT導入プロジェクトに目的がすり替わってしまっているのです。そのため、多くの企業が終わりなきDX地獄に陥り、費用と人的資源が浪費され続けているのです。ITシステムの導入を最終目的にしたDXは、もうやめましょう。
例えば、DXと称して、他社で実績のある、AI(人工知能)を用いた需要予測システムを導入したとしましょう。当然ですが、このシステムが現場のオペレーションに組み込まれ、活用されなければ、全く効果を生みません。さらに、オペレーションに組み込まれたとしても、消費者・顧客・市場からのフィードバックを反映し、日々AIアルゴリズムを最適化・高度化していない限り、自社が競合と差別化できるような、大きな価値を生むことはできません。
最も大切なのは、現場の従業員の意識改革と自走化です。「デジタル技術を武器として積極的に活用し、自社の価値をより高めたい」という意識を芽生えさせ「やったら本当に成果が出た」という成功体験を繰り返し、自信をつけてもらい、定着化していくことです。従業員自らが、課題設定を行い、デジタルをツールとして徹底活用し、トライアル&エラーを継続している、そういった「自走化」状態が作り出せるか否かが、成功と失敗の分かれ目なのです。
日本企業の変化を阻む厚い壁
しかし、この企業文化変革を成功させるためには、日本特有の構造的ハンディキャップを理解したうえで解決策を見つける必要があります。その内容は、2020年の秋にマッキンゼーのウェブサイトに掲載したDXレポートでも書きましたが、要点を紹介します。
- 経営陣の同床異夢:会社経営上の重要な意思決定は、幹部の合議制で決められます。それにより、本来トップダウンで進めるべきDXによる全社変革を、社長が一気に推進することができません。特にデジタルなど経験がない分野については、経営幹部の個々人で、理解度・優先度・リスク許容度も異なり、かつ現場の抵抗も予想されるので、合意に至るまで途方もない時間がかかります。
- 部門を分かつ厚い壁:開発・マーケティング、製造、営業の間の対立、さらにビジネス部門とIT部門の対立も、DXを阻害する大きな要因になっています。DXに最も必要な、顧客目線ではなく、部門目線が最重要視されます。またレガシー脱却などで忙しすぎてキャパがないIT部門と、DXで早く結果を出したいビジネス部門の間での闘争でDXが2年停滞したという例も珍しくありません。
- 世代間の闘争:経営幹部、管理職、現場、それぞれの階層における、デジタルに対する経験の違い、意識の違い、リスク・効果への解釈の違いが見られます。そもそもパソコンやスマホを触らない経営幹部と、スマホで何でもできるのが当たり前のデジタルネイティブ世代では、話がかみ合いません。現場からボトムアップにDXの施策を提案しても、上の意向を忖度した管理職に止められたり、経営陣に伝わったとしてもアクションが取られないなど、苦い経験を持つ若手の方が数多くいます。しかし、一方で「わが社はDXに力を入れる」とメディアに答える経営幹部を見て、現場が抵抗勢力化してしまうという例も見られます。
- 変化を阻む企業文化:変革スピードを、さらに遅くしているのが、時代に即さない企業文化が根強く残っていることです。例えば、石橋をたたいて壊してしまうくらいの失敗が許容されない文化。過去の失敗を繰り返さないために作られた無数のルール・不文律。さらに、出る杭は打たれるという特有の文化は、改革の推進を難しくしています。そして、大きな問題は、これらは過去数十年の歴史の中で培われたものであり、急激に変更すれば、現場からのさらなる抵抗や、顧客・消費者に対する価値の毀損につながるリスクがあるのです。
10年後の自社を救うのは、あなた
このような課題を持つ日本企業は、例えれば、巨大なタンカーです。目の前に氷山が迫っていても、急には止まれないし、方向転換もできません。もしかしたら、氷山にぶつかっても、巨大なタンカーの乗員は、しばらく気づかないかもしれません。この巨大なタンカーに、危険を知らせ、方向転換させるには、強力なタグボートが必要です。
タグボートを操るのは、もちろんこの本の読者の皆さんです。そして、皆さんはDXを刺激剤として使い、従業員の皆さんに向けて警笛を鳴らしてください。従業員は、恐怖を覚えるでしょう。「AIに自分の仕事を奪われる」「古い体質のうちがGAFAになれるはずがない」「忙しいのに、また兼務で新しい取り組みをやらされて大変だ」「DXなんてITベンダーに任せればいい」「いまでも十分利益が出ているのに、なぜあえてリスクを冒すのか」「DXなんて失敗した話しか聞かない」「どうせやっても評価されない」……言い訳や、批判は、いくつでも出てきます。だからこそ、DXは取り組むべき題材として素晴らしいと思います。いままでの会社の常識に疑問を呈することができるからです。そうやって生まれた摩擦の中から、何を変えるべきで、何を残すべきか、企業文化の取捨選択ができるのです。
本書はDXについての解説書であると同時に、日本企業を変革するうえで明らかになった様々な課題に対して、私たちが日々どうやって立ち向かってきたかの、戦いの記録でもあります。経営幹部の方はもちろん、特に10年後の会社の存亡のカギを握る、次世代リーダーの皆さまを対象に書きました。40・50代の勇者が、次々に立ち上がり、DXという武器を使って、企業文化変革を成功させる、その後押しになればと思っています。
本書では、DXを成功させるための要諦を、Why、What、How、そして、あなた自身が何をすべきなのか、という構成でまとめました。各章には、マッキンゼーが、これまで年間1200社のグローバル企業・日系企業のDXに携わってきた経験から培ったノウハウを、惜しみなく詰め込みました。企業のパフォーマンス向上と、人材育成の2つ。それこそがマッキンゼーのミッションだからです。
各企業の次世代リーダーの皆さまにノウハウをお伝えすることで、少しでも企業文化変革を実現できる企業が増え、しっかりと変革意識・変革文化を、従業員の一人一人に根付かせ、企業価値を高める活動を開始していただきたいと、切に願っています。
DXをバズワードや一過性のブームで終わらせるのは、もったいないことです。会社を変革するきっかけとして、そして、武器として、最大限活用してください。そして、10年後も、100年後も、日本が自律繁栄し、世界に貢献できる国であり続けるために、いまこそ、会社を変革しましょう。
この本は、変革を一緒に引き起こしてくださる、同志の皆さんに、少しの勇気と、少しのきっかけを与えられたらという思いで、マッキンゼーメンバーで総力を挙げて、書き上げました。一緒に、日本のDXの新たな歴史の一ページを刻もうではありませんか。
マッキンゼー・アンド・カンパニー
マッキンゼー・デジタル・パートナー
黒川 通彦
【目次】
【関連記事】
■はじめに:『マッキンゼー 勝ち続ける組織の10の法則』
■はじめに:『マッキンゼーが読み解く食と農の未来』