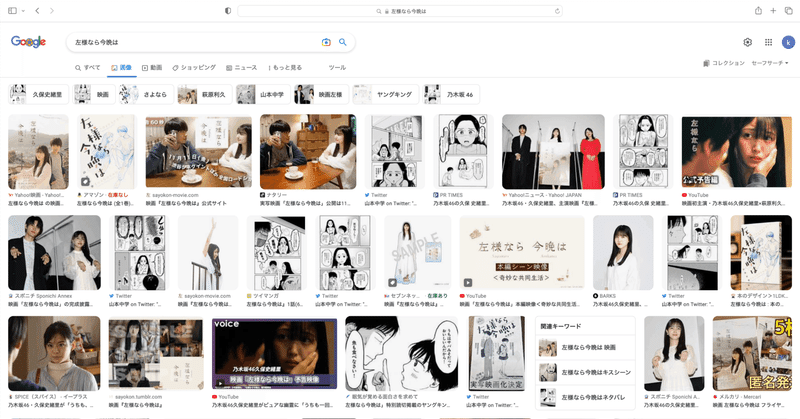
映画 「左様なら今晩は」 レビュー 青年漫画から少女漫画へ
原作は山本中学による漫画作品であり、同棲していた恋人にフられたごく普通のサラリーマン・半澤陽平と、彼の部屋に突如姿を現した幽霊・愛助の奇妙でハートフルな共同生活が描かれる。半澤陽平を萩原利久が、愛助を乃木坂46の久保史緒里がそれぞれ演じ、メガホンは高橋名月である。
前置き
久々に渋谷で映画を観た。パルコのシネクイントだ。渋谷で映画というと、上京したばかりの頃にシネマライズで新海誠監督の「秒速5センチメートル」を観て終演後には舞台挨拶もやっていて、たしか監督の他に音楽の天門さんも登壇しており、ファンだった私はえらく感激したというのが始まりの記憶である。細田守監督の「時をかける少女」が2006年7月の公開で当初わずか6館の配給にもかかわらず、口コミで配給を全国に増やし2007年の4月まで約9ヶ月の異例のロングランを記録した、その春のことだ。当時インディペンデントでまだアングラだったオリジナルアニメーション映画が15年のうちに雨後の筍のようにぽこぽこ作られるようになり、おまけに新海作品が東宝で配給されそれがもう3作目を数えるだなんて夢にも思わなかったし、「左様なら今晩は」と公開日が重なったその「すずめの戸締り」は渋谷のミニシアターではまったく公開されていないどころかシネマライズもアップリンクも閉館してもう無い、というミライも予想できなかった。
感想
長くなった前置きはさておき「左様なら今晩は」だ。率直な感想を先に言うと、いい意味で乃木坂オタのための映画ではなく、ちゃんと『映画』だった。漫画原作の映画化というもうそれだけで観に行きたくない!という人が出てきてもおかしくない状況の昨今、別物にすることなくしかしわざわざ映像にするからには、というなんともちょうど良い塩梅で、またアイドルを主演にという、何度目のあれなのか、ではなく(乃木坂46)はべつにいらないよね、というレベルにもっていっているのは高橋名月監督のプロットとディレクションの冴えと、監督と演者間の密で丁寧なすり合わせにあるように感じた。
広島県尾道市のフィルムコミッションありきの撮影であったと予想するが、それを逆手にとり久保史緒里演じる幽霊の愛助にバリバリの方言を喋らせて、なんとも親しみとそして真実味をもたせるというアイディアは非常に効果的であったように思うし、原作の『性』というテーマを巧みにぼやかすことに成功していたように思う。ヒロインがヒーローと同一言語をしゃべらないというのも、ある種ゲーム的な異世界もの全盛のこの時代にマッチしていて好感が持てた。これが原作通りに都会で標準語を喋っていたら深夜ドラマみたいな雰囲気になってしまっていたように思う。
さらにアイドルで映画といえば大林宣彦監督だが、奇しくもその尾道三部作に通ずるし、今作にもいい意味でのアマチュア映画感が宿っていて、画角には非常にこだわりを感じ、なおかつ美しくまとめていたように思う。無駄にカットを割らずに長回しなのも日本映画の文脈に沿っていて潔く、音楽もライトモチーフ的なメロディの支配感はいっさい無いがしっかり間が埋まるという絶妙さ。なんなら久保史緒里の演技も「時をかける少女」の原田知世みたいに瑞々しく、渋谷の坂でひとり、これはいいものを見た、と唸ったのだった。初出演で初主演というのはどうしたって記念碑的になるしプレッシャーもあったろうが、どうして素晴らしい演技だったと思う。おめでとうございます。
また半澤陽平を演じる萩原利久のどことなくふわふわした演技も、後述する『Z世代』という現代の若者たちドンピシャな空気をまとっていて、ああリアルだな、と思わせられて非常に心地よかったし、脇を固める俳優陣もそれぞれ誇張しないけれど確かにそこに存在しているというリアルさで、本当に地方都市のワンシーンを切り取ったように錯覚させられた。不動産屋のシーンは声を出して笑ったし、宇野祥平という絶妙な配役があのキャラクターを引き立てていたと思う。松尾スズキじゃなくてよかった。私は松尾スズキは好きだが。
残念だったのは、本当にリアルな地方都市感が出過ぎていて、もっと尾道の美しい景色を見せれば”映える”のになとかいうプロデュース思考が、観光PR映画を見すぎた脳にはどうしても浮かんできてしまって、「ドライブマイカー」だってロケを釜山でやる予定が広島に変わってたまたま美しいドライブシーンが撮れたってだけで映画の内容には関係なかったもんな、とかコロナ禍でいろいろ大変だったんだろうな、とかわざわざ自分で納得させる工程があったことぐらいである。
ここまでがざっくりとした感想で、もう少し深く掘り進んでいく上での重要なキーワードが、『Z世代』と『愛と物理法則』の二つである。ここからはネタバレを含む。
Z世代 ここからネタバレ
Z世代とは1990年代半ばから2000年代半ばまでに生まれた世代であり、2022年現在でいうと17歳から27歳あたりの若者たちを指す言葉である。デジタルネイティブであり、環境問題へのコミットメントや政治関心、LGBTQをはじめとする性への関わり方も、一つ上の世代であるミレニアル世代とは隔世している。そして主役の半澤陽平の設定は25歳と、ちょうどこのどまんなか。なぜこんなことをわざわざ書くのか、それはこの映画が最初から最後まで、この世代が主人公だということを理解しないとあまりに退屈に見えてしまうからだ。
なぜこの映画は同棲までしていた男をどう見ても超絶カワイイ幽霊に対してはわざわざプラトニックな風に描くのか。半澤陽平が優しくみえるのはなぜだ?しかも触れ合えるようになるにも関わらずだ。そして優しさは罪深いと説く同僚に対しても、据え膳というわりにあまりにも素っ気ないではないか。原作通りにトイレにこもって賢者タイムとはならない。また同棲を解消して出て行く元カノに、なんかごめんね、と言う陽平の言葉(これは原作にない)に対して、そういうところが本当にムカつく、という返し。きっと優しさは自己愛で、そこに元カノは嫌気がさしたのであろう、というのは原作通りだが、このあたりの原作にはないセリフの追加には監督の恣意性を感じるし、アイドルが主演の映画で青年漫画特有の全年代男子目線の『性』というテーマをどうはぐらかすか、むしろ思い切って少女漫画にしてみてはという大転換への解が、オスとしての強引さや貪欲さがあるようで見えてこず、なんでも検索窓に答えを求める、Z世代という他の世代から見るとなんだかふわふわしたよくわからないものという演出によってなされているのである。ここで断っておきたいのはZ世代を揶揄しているのではなく、3年ひと昔、どんどん時代は変わっていき、その世代ごとの価値観の相違はなかなか埋められず掴みづらいということである。
さらにこれは送別会のシーンでも描かれる。上司の、飲みに誘っても嫌がるかもと思って遠慮していた、という言葉に対して陽平は、誘ってくださいよ、と返す。だがその後のタバコミュニケーションは断るのである。同棲していた彼女の前では吸っていたのに、幽霊が見えてからはやめた、という演出。なぜだ?幽霊がアイドルだから?映像だけだと説明がつかないが、まあ別にタバコなんて吸っても吸わなくてもよかったんだろう。冒頭で陽平の喫煙シーンがあるが、手にタバコが全然馴染んでいないというか、わざわざかっこよくタバコを吸う仕草などを考えていた世代とは全く違うのである。これは偶然の産物か監督の采配か、後者であったら脱帽である。ちなみに私は1987年生まれのミレニアル世代(というよりゆとり初期)だが、少し上の先輩方はタバコがやめられない人たちばかりである。まさに隔世。デートシーンの陽平の私服も、ユニクロとGUで揃えた風で靴だけはニューバランスというバランス感覚、サイズ感はちょっとオーバーサイズで、まさに今この瞬間という徹底ぶり。
しかしこのあたりの原作の改編は苦心したであろうことが伺えるし、私は感心したが、やや伝わりづらいだろうなとも思った。それにしてもあの送別会の机に出ていた、ニラのような食材が生肉で巻かれた鍋、あれはなんだったのか気になって眠れないので誰か教えて欲しい。
愛と物理法則
次に、わざわざ青年漫画から少女漫画へと改変し主人公をプラトニックに描き、物語をカタルシスへと導く、「愛と物理法則」というテーマについてだ。
今作の設定では、物理法則は死んで幽霊になると崩壊する、としている。死の先にいっさいの法則は失われ、『無』になる。非常に仏教的な考え方だし、手塚治虫の「ブッダ」にも似たような記述はある。つまり、幽霊は縛られず自由だ、というのである。地縛霊とはいかに。『無』となった先にはまさに『無限』のエネルギーがあり、これが『愛』というエネルギーに変換された結果、愛助は輪廻転生にいたって十数年後に女子高生となり、おじさんになった陽平と再会するというのが結末なのだが、なんだか字面だけ見るとどこぞの仏教映画みたいだ(仏陀は解脱したのに再誕させちゃダメだぞ☆)。
映画での陽平と愛助の間には、奇妙な同居関係を続けていくうちに徐々に恋とも欲とも違う感情が育まれていく。それはつまり『愛』なのだが、原作では『性』に対する『欲』が互いに引き金となり、そのエネルギーは『愛』に変換され、徐々に互いに触れ合えるようになり(この記述は正しいようで正しくない気がする。陽平が触れたのではなく、愛助が触れられることができた、が正しいだろうか)、ついには人間と幽霊のセックスまでがなされてしまうが、映画ではもちろんずっとプラトニックなので、ハグも愛犬と飼い主のよう、キスのアングルは後頭部。まさに『愛』しか見えない状態が画面では展開されており、なんだか尊くて眩しいものをずっと歯痒い顔をしながらヒヤヒヤして見る、そうまさに幼子イエスに注ぐ20の眼差しよろしく、アイドルに対するファンの眼差し、推しに対するあの顔になって映画を見る羽目になるのである。監督は絶対狙っている。わからない人は置いてけぼりというのもなかなかに気持ちがいい。
これは完全な憶測だが、愛助の『愛』へのエネルギー変換はおそらく陽平が引っ越してきてから徐々に行われており(つまり陽平に惹かれていった)、その漏出が青年漫画である原作とリンクしているはずの映画世界を同棲解消というきっかけで崩壊させ、その後に少女漫画世界へと書き換えられたというのも、あながち間違ってはいない予想なのではないだろうか。さらに映画と原作での違いで言えば、原作では全く違う人間として転生しているのに対し、映画では愛助の記憶を有していることが仄めかされており、そのあたりの好みは別れそうだ。ちなみに世界を書き換えた愛助登場シーンも完全にジャパニーズホラームービーの文脈で、見応えがあった。
終わりに
最初に記した通り、このうえなく『映画』だった。すべてちゃんと文脈にのっとった上で、さらにアイドル映画としても完成させた高橋名月監督に拍手を送りたいし、瑕疵の無い演技を見せた俳優陣に同じく賛辞を送りたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

